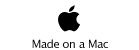2014年9月2日火曜日
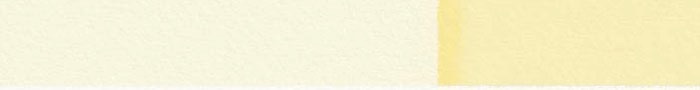
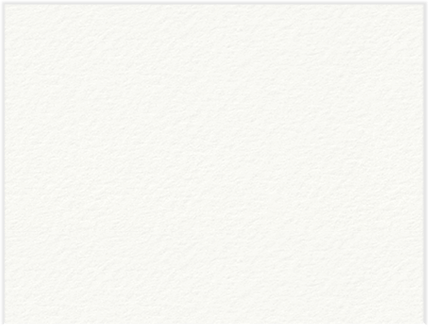

第12回国際カワウソ会議
8月11日から15日まで、ブラジルのリオデジャネイロで第12回国際カワウソ会議が開催され、参加した。3年ごとに国際自然保護連合種の保存委員会カワウソ専門家グループが開催する会議で、今回の参加者は、南米の研究者が主体で百数十名が参加した。アメリカ、ヨーロッパやアジアなどからの参加者が少なく、少し残念な会議となった。発表自体は、南米の研究の盛り上がりを証明し、DNAを使った個体群構造などの研究が普通に発表されていて、レベルの高いものであった。残念な事に、東南アジアのカワウソの研究発表は私一人しかいない。日本からは、私以外に農大の安藤先生のグループが参加した。熱帯地方の雨期のカワウソの生態について東南アジアと比較したかったので非常に良い機会であった。アマゾンでも雨期には水が川から森の中に入って行き、水面から木が生える状態になる。乾期には川に活動が集中していたカワウソも雨期になると森に入って行って生活していた。まったく東南アジアと同じである。ただアマゾンでは氾濫原に生えた熱帯雨林であるのに対して、東南アジアは多くが泥炭湿地林でこのような状態が起こる。会議の後、ポストコングレスツアーといって、研究者が調査地に案内してくれる事が多く、今回も、17日から22日までトカンティス州の州立公園に行き、アマゾンの熱帯林と、半乾燥林の両方を訪れる事ができた。熱帯林はオオカワウソとシンネッタイカワウソの生息地である。オオカワウソは昼行性であるので、何とか観察しようと毎日10km以上歩いたが、残念ながら、ちらっと川を泳いでいるのを見ただけであった。カワイルカはボートの横を泳いでくれた。なかなか実り多い学会であった。



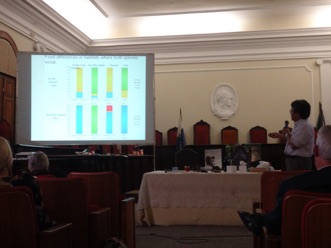

アマゾンの熱帯林が保護されているカンタオ州立公園でオオカワウソ探し。この時は、ピンクドルフィンが横を泳いでくれた。
東南アジアの研究発表は私だけ
半乾燥地域にある州立公園も訪れたが、乾期であるため至る所で火入れが行われていて、夜移動したら道脇でも燃えていた。とてもコントロールできているようには思えず、森がどんどん減って行き、植樹までする段階になっている。トカンチィス州は、ブラジル一貧しい地域からもっとも成長している地域に変貌したが、トウモロコシや大豆を生産して中国に輸出するために、大量の殺虫剤が土壌に撒かれてて、他の生物が育たないとブラジルの研究者は批判していた。州の真ん中を流れるトカンティス川には、いくつもの巨大ダム湖が作られ、その代償措置のお金で州立公園なども運営されている。
ちょっと寂しいアジア地区ミーティング
ちょっと良さげな写真を撮って頂いたので載せました。オオカワウソの登場を待っている時